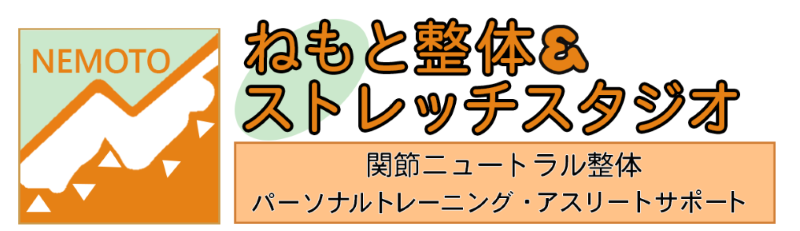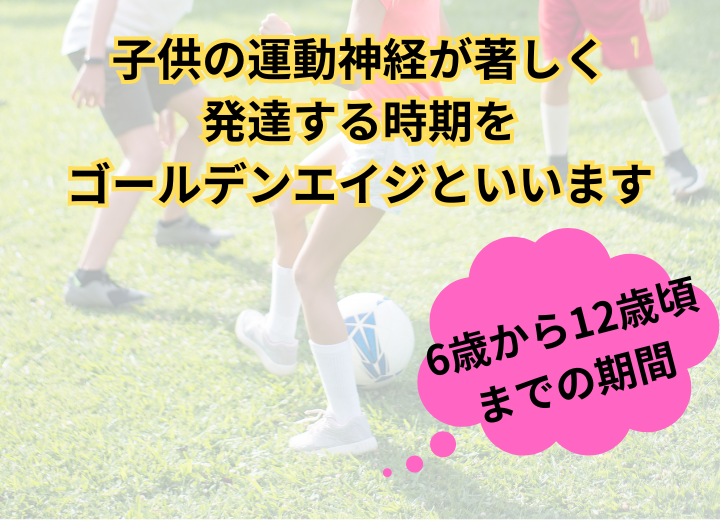U-8~10までにサッカーなどのフィジカル能力は決まります。

将来のトップアスリートを目指す子どもたちにとって、8歳までの時期は極めて重要です。特に川崎市では、川崎フロンターレの久保建英選手や三好康児選手など、世界で活躍する選手を多く輩出してきました。
本記事では、17年の指導実績を持つパーソナルトレーナーが、U-8世代に必要な専門的なトレーニング方法と、その重要性について解説します。子どもの可能性を最大限に引き出すための、保護者・指導者必見の情報をお届けします。

私がいる川崎市は川崎フロンターレが有名ですが、少年サッカーが非常に盛んな地域で16年続く、パーソナルトレーニングジムのねもと整体&ストレッチスタジオにも多くの子供たちがコンディションングやパーソナルトレーニングに通われています。
私自身は、幼稚園、小学生、中学生とサッカーもやっていましたが、高校・大学・社会人では主に格闘技・武道が専門でした。
現在は県立高校の男子バスケットボール部とフィジカルトレーナーの契約をしたり、エニタイムフィットネス向ヶ丘遊園ANNEX・向ヶ丘遊園・生田・登戸と提携しパーソナルトレーナーとして活動させて頂いております。
本記事では、川崎市の少年サッカーの保護者や指導者の方にも参考になる話を書いてみたいと思います。

川崎フロンターレ・中野島FC・パーシモンFCからトップアスリートが発掘

川崎フロンターレから三好康児選手、板倉滉選手・田中碧選手・三苫薫選手が育成され、柿生のパーシモンFCから久保建英選手、中野島FCにも川崎フロンターレの前に三好康児選手が所属していたと聞いています。
最近では中野島の近くに、神奈川県川崎市多摩区生田にあるスポーツ施設フロンタウン生田もでき、今後益々、少年サッカーが盛んなエリアになってくると思います。
ゴールデンエイジという言葉を知っていますか?
9~12歳までの時期で生涯のうちで最も運動神経を良くすることができる時期だということが分かっています。
私自身もスピードトレーニングコーチとしても、子供のスポーツ団体やトレーナーの専門学校、高校・大学の指導を長年行ってきました。
やはり、トップアスリートになるには、10歳前後に多方向・多刺激の動き作りが必要だと常々感じてきました。
その為、川崎市だけでなく、全国に対応した親子トレーニングの教材も制作したり、またその後の指導で何をジュニアアスリートの時期に必要としているのか?分かってきました。

小学生から柔軟性と筋力を高めて痛めない体作りを!

小学生で膝や腰が痛いというスポーツをしている子供達も多くご来院されています。通常は、整形外科に通院すると思いますが、レントゲンやシップの対応では大事な競技生活の時期もいつの間にか?過ぎていってしまいます。
賢い考え方としては、将来にどのようなリスクと現実が待っているのか?指導者や保護者の方がまず学ぶことが必要です。
私自身も自分の子供たちがスポーツをしてきた際に、知識不足で対応が間違っていたり、後悔しきりです。
私自身、毎日子供たちトレーニングをしてきて、年代に合わせた必要なセルフケアとトレーニング方法が確立できました。

「なんか変だな…」に気づく力が未来を守る
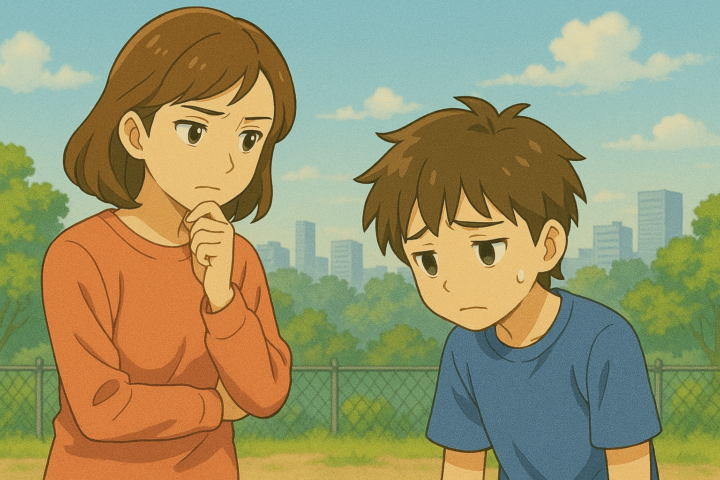
成長が盛んな時期の子どもたちは、体の動かし方や感じ方が日によって変わることがあります。
「昨日まで平気だったのに、今日は足が重たい」「急に動きがぎこちない」そんな様子に気づいたとき、大人のちょっとしたサポートがとても大切です。
まず大事なのは、毎日の体の使い方を見直すことです。運動や遊びでたくさん体を動かす子どもは、知らず知らずのうちに同じ部分に負担をかけていることがあります。
動く前には軽く体を動かして筋肉を目覚めさせ、終わったあとには、使ったところをゆっくり伸ばしてリセットする時間をとりましょう。
疲れをため込まないことが、ケガの予防にもつながります。
また、「今日はいつもと違うかも?」という変化に気づけるよう、親子で一緒に簡単な体調のメモをとるのもおすすめです。
「朝からちょっとだるそうだった」「練習の途中で休むことが増えた」など、小さな気づきを積み重ねていくことで、無理を避ける判断がしやすくなります。
運動量やスケジュールの調整もポイントです。がんばる気持ちは大切ですが、ずっと全力で動き続けていては疲れもたまりがち。
週の中で「しっかり動く日」と「ゆっくり過ごす日」のバランスをとることが、元気な毎日につながります。
特に長い練習が続く時期は、中休みの日を意識的につくることも必要です。
心のゆとりと環境の工夫が、ケガを遠ざける

心のコンディションにも目を向けましょう。
練習や試合のたびに高い目標を掲げるよりも、「今日はここだけ意識しよう」といった、取り組みやすい目標を自分で立てていくほうが、達成感も得やすくなります。
そして、その小さな達成を一緒に喜んでもらえることで、自信ややる気につながっていきます。
仲間との関係やまわりの雰囲気も、子どもにとっては大きな影響があります。
良いプレーを言葉で伝えたり、困っているときに声をかけ合えたりするような空気があると、安心してのびのびと活動できます。
時には言葉にならない不安やプレッシャーを感じていることもあるので、日常の会話の中で気持ちを聞いてあげる機会も大切です。
また、体に直接関わる環境づくりも見逃せません。
たとえば靴。サイズが合っていないと、足元からバランスをくずしてしまうことがあります。
履き心地やすり減り具合をときどき確認し、必要なら早めに調整しましょう。
練習中に不安を感じたときは、テーピングやアイシングなど簡単な対処法を知っておくだけでも安心感が生まれます。
子どもの体は、日々成長と変化を繰り返しています。
そのときどきの様子に目を向けて、無理のない範囲で運動や活動を続けられるよう支えていくことが、長く元気に楽しむための土台になります。
「今日はどうだった?」の一言や、そっと手を差し伸べるだけでも、大きな支えになるはずです。
「今だけの成長」を逃さないために
〜ゴールデンエイジに身につけたい体の土台〜

8〜10歳は運動能力の土台を作る重要な時期です。
特に9〜12歳は「ゴールデンエイジ」と呼ばれ、あらゆる動きを吸収しやすく、体の使い方を自然に覚える貴重なタイミングです。
この時期にどんな経験を積むかが、将来の体の動きやケガのしにくさに大きく影響します。
たとえば、走る・止まる・ジャンプするだけでなく、横や斜めに動いたり、急に方向を変えたりする練習を取り入れると、バランス力や反応の速さが育ちます。
遊びの中に取り入れやすい多方向ジャンプやジグザグ走などの動きは、楽しみながら神経系を刺激することができます。
また、柔軟性や筋力の向上も忘れてはいけません。
無理のない範囲で股関節や足首をしっかり動かすことで、ケガの予防につながります。
年齢に合ったストレッチや簡単な体幹トレーニングを習慣にすると、成長を支える体の準備が整っていきます。
子ども自身が「今日は少し重たいな」「足が疲れてるかも」と気づけるようになることも大切です。
練習後に「どんな動きができた?」「疲れはどうだった?」と声をかけるだけで、体と向き合う習慣が少しずつ育っていきます。
子どもの“気づく力”を育てる環境づくり
〜整えるのは練習だけじゃない〜
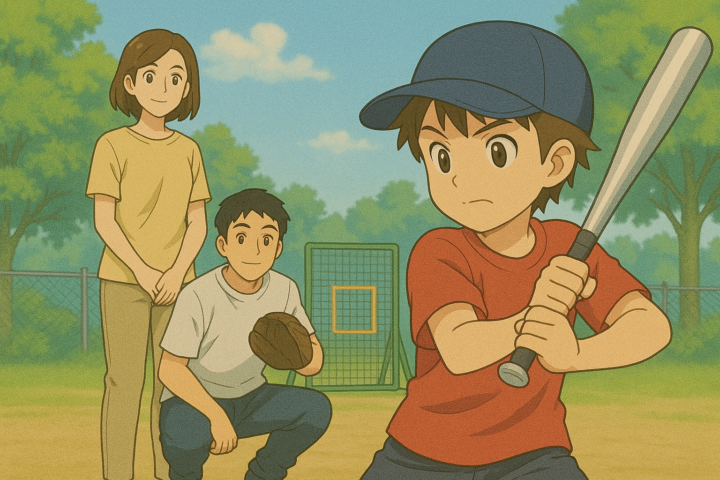
体の成長を支えるのは練習だけではありません。
たとえば、1週間のスケジュールに「動く日」と「休む日」をあらかじめ決めておくだけで、無理を防ぐことができます。
体を休めるタイミングを見える形にしておくことで、がんばりすぎを防ぐきっかけになります。
また、シューズの見直しも見逃せません。
サイズが合っていなかったり、すり減ったまま使い続けていたりすると、体のバランスが崩れやすくなります。
数か月ごとに足の状態や履き心地を確認し、必要があれば適切なものに変えるようにしましょう。
さらに大切なのは、大人が「管理する」のではなく、「選べる力を育てる」ことです。
「今日はどうだった?」「どんなケアをしたら良さそう?」と問いかけることで、子ども自身が体の変化に気づき、対処方法を考える力が育ちます。
この時期の体づくりは、目に見える成果ばかりではありません。
毎日の小さな気づきや工夫の積み重ねが、未来のケガを防ぎ、パフォーマンスを引き出す基礎になります。
ゴールデンエイジは、今しかない貴重な時間。その時間をどう過ごすかが、将来の可能性を大きく広げていきます。
ジュニアアスリートのバランス能力・スピードアップ・怪我の予防
根本が17年トップアスリートまで指導してきたトレーニングをパーソナルトレーニングで小学生から学べます。
体験60分コースから10回チケットで自分のペースで通えます。
川崎市スポーツ整体|アスリート専門 コラム スピード&パワートレーニングに関連する記事