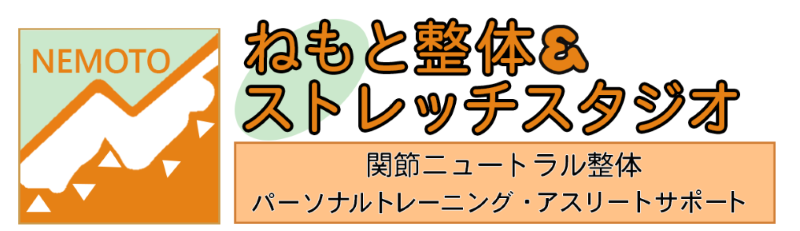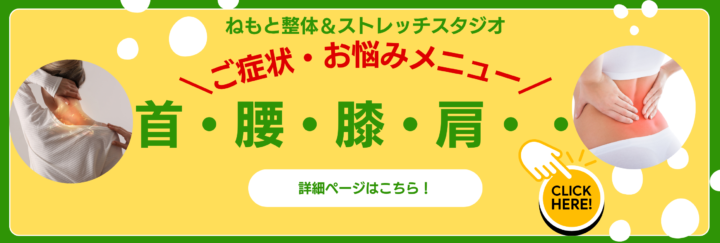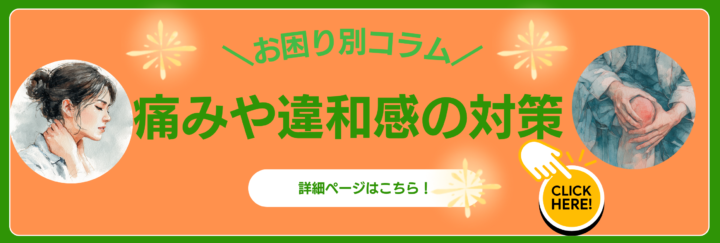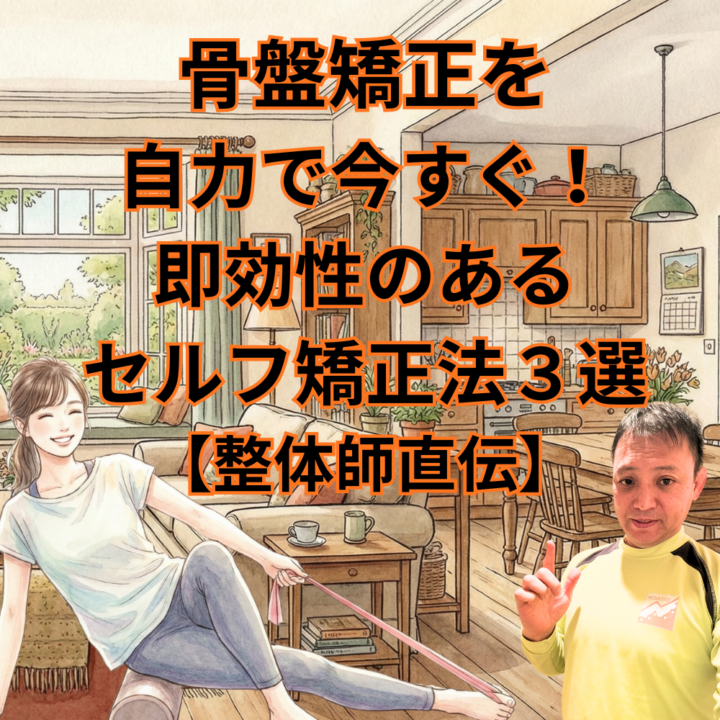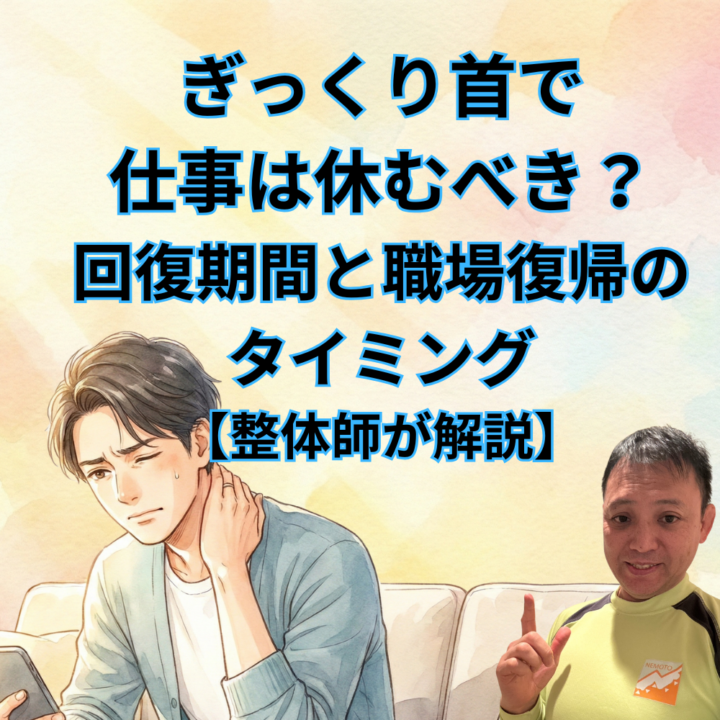なぜ椅子スクワットが効果的なのか?専門家が推奨する理由

ねもと整体&ストレッチスタジオ院長根本大
川崎市登戸・向ヶ丘遊園の「ねもと整体&ストレッチスタジオ」院長 根本大。20年の臨床経験を持つ関節ニュートラル整体の施術者。健康運動指導士・米国ストレングス&コンディショニングスペシャリスト。整体技術と運動指導の両面からのサポートしており、長年の経験をお伝えしています。

スクワットは私も一押しのエクササイズですが、お客様にスクワットをまず始めましょうとお話しすると、「自分ではなかなかできない」という方がかなりいらっしゃいます。
スクワットは正しいフォームで行うことが重要ですが、実際にはフォームが奥深く、自分で完璧なフォームでできる方はかなり少ないのが現実です。我々トレーナーが専門的に指導しても、正しいフォームが習得できるまで時間がかかります。しかし、ある方法を使うとすぐにスクワットを導入することができます。
それが今回ご紹介する椅子を使ったスクワットです。
スクワットのフォームはなぜ難しいのか?

スクワットのフォームがなぜ難しいかというと、正しいフォームでやろうとしても、いくつもの注意点があると体が思うように動かないものです。例えば、膝が出過ぎてはいけないと思うと腰が反ってしまったり、深く下げようとしたら腰が曲がってしまったり、膝が内側に入ってしまって膝が痛くなったりと、様々な注意点があります。
しかし、後ろに椅子を置いてスクワットするだけで、フォームがかなり安定してきます。それは椅子が後ろにあることで骨盤が前傾しやすく、自然と正しいスクワットの動作に近い動作を行ってもらえるからです。
椅子スクワットとは?初心者にも安全なトレーニング法

椅子スクワット(いすスクワット)は、椅子を使って行うスクワットの一種で、通常のスクワットよりも膝に負担が少なく、運動不足の方や高齢者の方でも安全に取り組めるトレーニング方法です。Chair squat(チェアスクワット)とも呼ばれ、自宅で簡単にできる下半身強化エクササイズとして人気が高まっています。
ただし、ほとんどの方が椅子を使ったスクワットを実践しているケースは少ないと思われます。「スクワットをやった方がいいですよ」ということをお伝えすると、「スクワットは難しくて」と返答される方が多いからです。そう言って、起立・着席を行うように「こうやって実践してみてください」とお伝えすると、実践していただく方も多くいらっしゃいます。
これが椅子がないと、私たちトレーナー目線で正しいスクワットを行える方というのはかなり少ないはずです。どこに注意点を置いたらよいのかということに個人差があるので、動作の修正が必要になるからです。
椅子があることで、しゃがむ角度も目安になることから、一度動作を覚えれば、テレビを見ながらでも安全に行うことができる、おすすめのスクワット方法になります。
柔軟性に応じて、ワイドスクワットなど個別な対応が必要

スクワットには一つ難点があって、体が硬い方はしゃがみづらく、そもそもスクワットの動作自体ができないということが挙げられます。動作自体ができないので、回数を重ねていくとどうしても関節の負担が強くなってしまいます。
このような場合の解決策として、足の幅を広く行うワイドスクワットを行うことも有効なテクニックです。ワイドスクワットは通常、内転筋群が中心になってしまうので、標準としてはノーマルのスクワットの方がおすすめですが、体が硬い方はワイドスクワットでも、そこまでつま先が外に開き過ぎなければ、脚全体にも効くスクワットとして利用できます。
ケースバイケースとして、標準のスタンダードなスクワットをできれば行い、それも厳しいようでしたら足幅を少し広めに行っていただくとやりやすいと思います。椅子を使ったスクワットが最もイメージがしやすいと思いますが、椅子がないとできないようだとスクワットの習慣が難しくなってしまうので、そういった面でもぜひワイドスクワット気味のスクワットも取り入れてみてください。
椅子スクワットから椅子なしのスクワットの移行

椅子の前に立ち、足幅は肩幅程度に開いて、足の向きは軽く外向きにします。背筋を伸ばし、胸を張った状態で準備姿勢を取ります。息を吸いながらゆっくりと腰を落とし、椅子に軽く座るように、お尻を後ろに突き出します。椅子に座っていたフォームのまま、できる方はさらに深く太ももが床と平行になるまで下げたら、息を吐きながら立ち上がります。
動作中は膝がつま先より前に出ないように注意し、背中は丸めず、胸を張った状態を保ちます。重心は踵に置き、膝が内側に入らないよう、足の向きを意識することが大切です。
椅子を使った方法で骨盤の角度や体幹の安定、膝の正確な向きを習得し、徐々に椅子なしで、椅子を使った方法よりもさらに深い角度でスクワットが行えるようになると、トレーニング効果が格段に向上します。
片足スクワットを椅子を使うことで得られる効果

椅子を後ろに置くことで様々な効果が得られます。まず、椅子があることで自然と骨盤が前傾位置に保たれ、正しいスクワットに必要な姿勢が無意識に作れるようになります。
また、後ろに椅子があるという安心感で、深くしゃがみやすくなり、恐怖心なく正しい可動域で動作できるようになります。
さらに、椅子に座る動作により、自然と正しい軌道が身につき、複数の注意点を同時に意識しなくても、正しい動作パターンが習得できるのです。
片足椅子スクワットのやり方

より負荷を高めたい場合は、片足スクワットも効果的です。椅子の前に立ち、片足を椅子の上に乗せて、地面についている足で体重を支えながら、ゆっくりと腰を落とします。片足に集中的に負荷をかけることで、より効果的なトレーニングが可能になります。
椅子を使った片足スクワットは、トレーニング用のベンチと違って不安定なものもあるため、バランス能力が低い方は十分注意して行ってください。
片足スクワットの注意点として、つま先と膝の方向を必ず同じ方向にするということがポイントです。膝が内側に入ってしまうと膝を痛める要因にもなりますので、向きを注意することが大切です。
片足スクワットからさらに負荷を増やすことも可能です。

椅子スクワットは下半身の筋力強化に非常に効果的で、大腿四頭筋、ハムストリング、大臀筋を効率的に鍛えることができます。
筋肉量が増えることで基礎代謝が向上し、脚やせ効果も期待できます。また、適切な負荷で膝周りの筋肉を強化することで膝痛予防にもつながり、体幹の安定性も向上してバランス能力の改善も見込めます。
慣れてきたら、ダンベルを使って負荷を強くすることが可能です。ダンベルは片手で画像のように行ってもよいですし、両手でも大丈夫ですが、ダンベルを落として足に落とさないよう注意してください。このように椅子を使うことで、スクワットは段階的にも負荷を強くすることができます。
ジムに行かないと筋肉をつけたり筋力アップができないと思い込んでいる方も非常に多いですが、椅子を使ってスクワットを行ってから片足スクワット、さらにはダンベルを持って片足スクワットまで行うと、中級者レベルまで十分筋力を向上させることが可能だと考えます。
スクワットのバリエーション スプリットスクワット

スプリットスクワットは、このような姿勢で行うトレーニングですが、片足を前に、後ろ足は後ろに引いて、そのまましゃがむスクワットです。ランジはその場から一歩前に足を出してしゃがみ、後ろに戻りますが、スプリットスクワットは体重移動を行わず、そのままの位置でしゃがむ動作です。
このトレーニングも、大腿四頭筋、ハムストリング、大臀筋など下半身の効果的なトレーニングです。正しい関節の使い方が通常のスクワットと異なるので、関節のストレスを軽減したり、バランスがスクワットと異なるためバランス能力を向上させるなど、メリットがあります。
椅子を使った片足のスクワットができない方は、スクワットとこのスプリットスクワットを組み合わせても、バランスの良いトレーニングメニューになると考えます。
まとめ
椅子スクワットは、英語でChair squatと呼ばれ、自宅で簡単にできる効果的なトレーニング方法です。正しいやり方を身につけ、自分のペースで継続することで、下半身の筋力強化や筋肉をつける効果が期待できます。
椅子を使うことで安全性が高くトレーニングできますが、中級者以上の方も片足スクワットにするなど、負荷を強くすることにも利用できます。
ただし、椅子を使った時に高齢者は特に気をつけていただきたいのが転倒です。椅子がどこにあるのかしっかり把握して行わないと、転倒してしまうと怪我にもつながります。
ただ、そのような負荷というのは日常的にも起こりうるものだと思うので、十分に怪我に配慮しながらトレーニングすると、ジムで行うトレーニングのような質の高いトレーニングも十分可能です。
ぜひ皆さんにも導入していただき、周りにもチェアスクワットを普及させていただければ幸いです。
椅子スクワット完全マスター診断テスト
あなたの椅子スクワットに関する知識レベルをチェックします。正しいやり方から高齢者向けまで完全マスターを目指しましょう。
Q1椅子スクワットの最大のメリット
Q2通常のスクワットフォームの難しさ
Q3椅子の効果メカニズム
Q4体が硬い人への対処法
Q5正しい椅子スクワットの姿勢
Q6片足椅子スクワットの注意点
Q7負荷の段階的向上
Q8高齢者の安全配慮
登戸ねもと整体&ストレッチスタジオの「当院のご症状・お悩みメニューまとめ」と「お困り別コラムまとめ」は下記になります。腰痛(坐骨神経痛・ぎっくり腰・分離症・すべり症・腰椎椎間板ヘルニア)肩こり(頚椎症・頚椎椎間板ヘルニア・巻き肩・ストレートネック)膝痛・腱鞘炎など症状・お悩みの個別ページに飛ぶことができます。