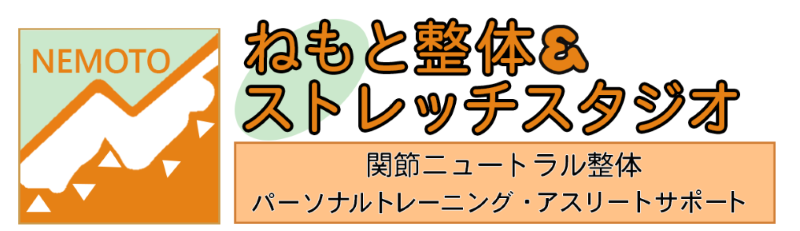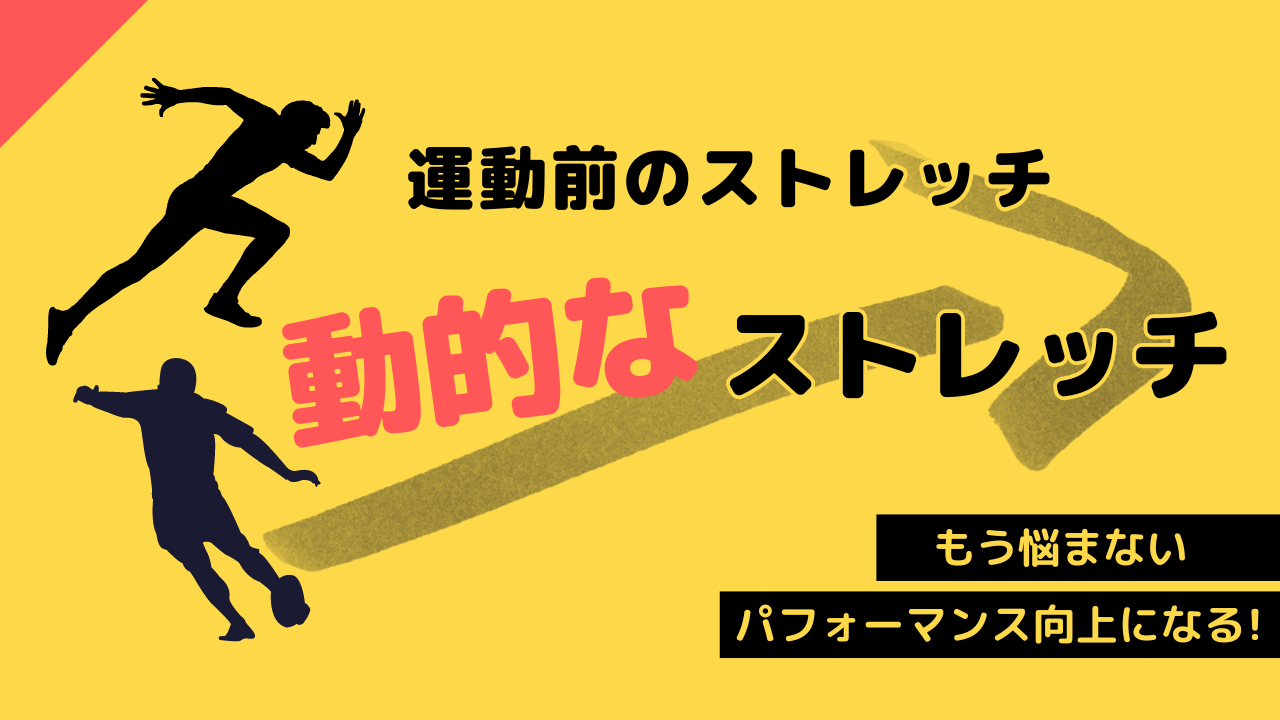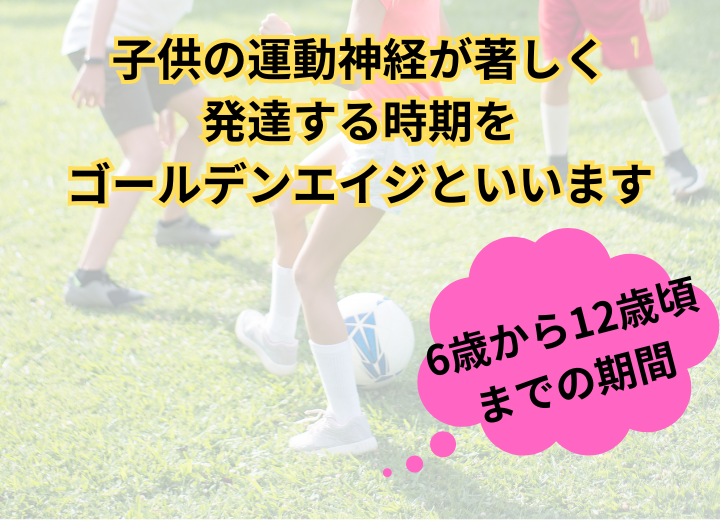運動前のストレッチは静的ストレッチではなく動的ストレッチです

運動前のストレッチ、あなたは正しく行えていますか?
多くのアスリートや指導者が、ウォーミングアップとクールダウンで同じストレッチを行う誤りを犯しています。
本記事では、パフォーマンス向上と怪我予防のための適切なストレッチ方法と、特にジュニアアスリートの育成における重要性について、プロのトレーナーの視点からわかりやすく解説します。
運動前の静的ストレッチから動的ストレッチへの転換が、なぜアスリートに必要不可欠なのか、その理由と具体的な方法をお伝えしていきます。

アスリートにはストレッチの導入がいかに重要かお伝えしていきます。プロのトレーナーがいないスポーツの現場では、いまだに運動前にストレッチをしてパフォーマンスや怪我の予防ができていない環境が多くあります。
これはチームの指導者の方を責めているのではなく、競技の指導者とスポーツトレーナーとしての役割が全く違うので、ご理解いただければ幸いです。
例えば、強豪校と言われている高校や大学の運動部も私も度々指導することがありますが、ウォーミングアップとクールダウンが同じことをやっている選手と言うのも実は多いです。
これから運動する競技に対しての体の準備を最大限に高めるウォーミングアップと、練習やトレーニング後の体をリカバリーするクールダウンで全く真逆なことが、同じことをしている選手が非常に多いのに驚きを隠せません。
これは学校体育でも部活のレベルでも多く行われていることです。
アスリートストレッチメニューで大事パフォーマンスを向上させたい!モチベーションアップの動的ストレッチ

とにかく、ウォーミングアップを行い、自然と体が動かせる状態になると言うことが準備として必要になるのは皆さんもわかりますよね?
それは腿上げでもいいし。
腕振りでもいいです。
運動がどうしても気が乗らない!運動が好きではない!と言うのは大人だけではなく子供にも多いと思います。
私は運動するのが嫌いだから、
ウチの子は体動かすのが好きではないみたい。
そういったお話もよく聞きます。
しかし運動と言うのは体にとってメリットが大きいですし、やらないよりやったほうが良いことは間違いありません。
スポーツではトレーニングしないで強くなることもありません。
大事な事はどのようなメリットがあるのか?どのように準備運動したら運動が行いやすくなるのか?といったことを知識として知り、再現できるように指導されることが、あなたがご自身やご家族のスポーツの動きや運動自体の楽しさを知るために最も重要なことです。
少しのことを学び、できることから実践することで、運動することということの楽しさや、爽快さを体験していただきたいと、私は常々思っています。

ジュニアアスリートストレッチメニュー子供のスポーツ将来は10歳前後で決定づけられます。

子供の時は特に運動のパターンをできるだけ覚えさせるということが大人になって障害体が動かすことに対して抵抗なく動ける基礎になります。
子供の時にと言うのは10歳前後のゴールデンエイジと言われている。年代がピークを迎えます
スポーツの世界でトップレベルに達するためには、実は10歳前後で決定付けられると言われています。
もちろん競技にもよりますが、1度動きを獲得すると、体の使い方と言うのは意外に体に残るものです。
様々なスポーツ。特に海外では3種目子供の時に行った方が良いと言われていますが、日本のスポーツの競技では複数行うほど時間的な余裕や環境は無いと思います。
そのためできるだけ早くから運動パターンをご自宅で教え込むということが、鉄は熱いうちに打てと言うこととなります。

「今日はなんだか体が軽い」そんな日をつくる準備運動の力

運動を始めたばかりの人でも、長年続けている人でも、よくあるのが「動き出しが重い」「すぐに疲れる」「なぜかケガをしやすい」といった悩み。
その原因の多くは、ウォーミングアップが“なんとなく”で済まされていることにあります。
準備運動の目的は、ただ体を温めることだけではありません。
ケガを防ぎ、関節の可動域を広げ、そしてパフォーマンスを引き出すまさに運動の土台になる時間です。
おすすめは、まず5〜10分の軽いジョギングから。最初はゆったりと、会話ができるくらいのペースで構いません。
徐々にテンポを上げていくことで、血流が促され、筋肉や関節が目覚めていきます。
体が温まってきたら、サイドステップや方向転換を加えるとより効果的です。
その後に行うのが、動的ストレッチ。たとえば、その場で膝を高く上げる「腿上げ」、軽やかなスキップ、ランジウォークなど。
肩や体幹、ふくらはぎも忘れずに動かしましょう。
この段階で意識したいのは、「止まらずに動きながら伸ばす」こと。
筋肉を実際の動きの中で準備させることで、動作のなめらかさが変わってきます。
特に大人の場合、仕事や家事の合間で運動することが多く、体がまだ“仕事モード”のままなこともしばしば。
ウォーミングアップは、そのスイッチを「運動モード」に切り替える大切な儀式とも言えるのです。
「動いたあとが変わる」疲労を残さないクールダウンのすすめ

そしてもう一つ、見落とされがちなのが「終わり方」。
運動が終わったあと、すぐにシャワーや帰宅へ向かっていませんか?
実は、クールダウンの質が翌日の体の軽さに大きく影響します。
まずは軽いジョギングやウォーキングを5分ほど行って、心拍数を徐々に落ち着けましょう。
急に動きを止めると、筋肉に疲労物質がたまりやすく、だるさや筋肉痛の原因になります。
そのあとで、静的ストレッチを取り入れます。
太もも・ふくらはぎ・腰回り・肩など、使った部位を中心に、深呼吸しながらじっくりと伸ばしていきます。
クールダウンは「体をリセットする時間」です。
動いたことで生じた緊張やクセを、整えてから1日を終える。
その積み重ねが、次の運動への良い循環を生み出してくれます。
多くの人が、運動そのものには意識を向けますが、「始まり方」と「終わり方」には無頓着なままです。
けれど、じつはこの前後の時間が、ケガの予防やパフォーマンスの向上、そして“続けられる体づくり”の鍵になるのです。
「今日はなんだか体が軽いな」
そう感じられる日は、突然やってくるわけではありません。
日々の準備と、終わりのケアを丁寧に積み重ねていくことで、自然と体が変わっていきます。
「また動きたくなる体」は、自分の手でつくっていけるのです。
「そのストレッチ、いつやるべき?」運動前後で分けたい本当の理由
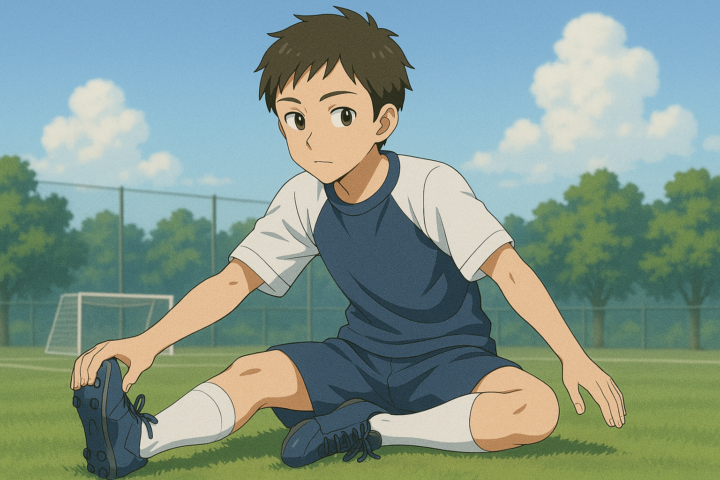
土曜の朝、公園の片隅で見かけたスポーツ少年団の練習。
子どもたちが輪になり、アキレス腱を伸ばしながら静かにカウントをしている。まるで儀式のようなストレッチ。
一見、ちゃんと準備しているように見えます。けれどその様子を見ながら、私は心の中でつぶやきました。
「これ、本当にウォーミングアップになってるかな?」
運動前に行うストレッチといえば、足を伸ばす・座って体を倒す…そんな“静的ストレッチ”を思い浮かべる人が多いかもしれません。
でも実は、体を動かす前にじっと筋肉を伸ばしてしまうと、かえって動きが鈍くなったり、ケガのリスクが高まることもあります。
本来、運動前に必要なのは「動きながらほぐす」動的ストレッチ。
腿上げ、腕振り、スキップ、ランジウォーク…。
これらの動きが体を徐々に温め、関節の可動域を広げ、頭と体のスイッチを“運動モード”に切り替えてくれます。
ところが、現場ではウォーミングアップとクールダウンが同じメニューで済まされていることも少なくありません。
運動前後では目的がまったく違うのに、やることが同じでは効果も半減です。
「今日はなんだか体が軽い」
そう感じる日は、実は始まり方に秘密があるのです。
「やってよかった」と思える運動体験を子どもたちに

体を動かすのが苦手な子ほど、準備運動の段階でつまずいていることがあります。
いきなり難しいことをやろうとすると、やる気がそがれてしまう。
けれど、腕を振る、膝を上げる、スキップする、そんな基本的な動きから始めていくと、自然と笑顔が出てくる瞬間があります。
大切なのは、動きやすさを体で実感すること。
そして「動くって、ちょっと気持ちいいかも」と思える体験を積み重ねること。
運動の前は“体を起こす時間”。
そして運動の後は“体を落ち着かせる時間”。
クールダウンでは、軽く歩いたり、ゆったりした呼吸を意識しながら静的ストレッチで筋肉を整える。
これだけでも翌日の疲れ方が変わってきます。
特に、**10歳前後の“ゴールデンエイジ”**と呼ばれる時期は、運動の型や感覚を覚える力がとても高い大切なタイミング。
この時期に、正しい準備や整理運動を知っているかどうかで、将来の体の動かし方に大きな差が生まれます。
けれど現場では、「とりあえず同じメニューでやっておこう」という空気が残っているのも事実です。
だからこそ、私たち大人ができることはひとつ。
その場その場に合った動きを選ぶ力を、子どもにも大人にも届けていくこと。
準備の内容が変われば、運動そのものの感じ方が変わる。
終わり方を整えれば、明日また動きたくなる。
運動は「がんばるもの」ではなく、「またやりたくなるもの」に変えられるそう信じて、今日も動きのはじまりに目を向けています。
川崎市スポーツ整体|アスリート専門 コラム スピード&パワートレーニングに関連する記事