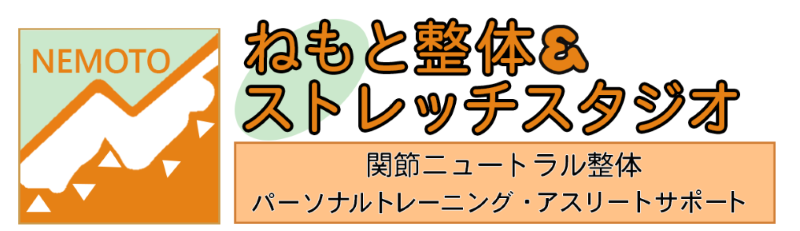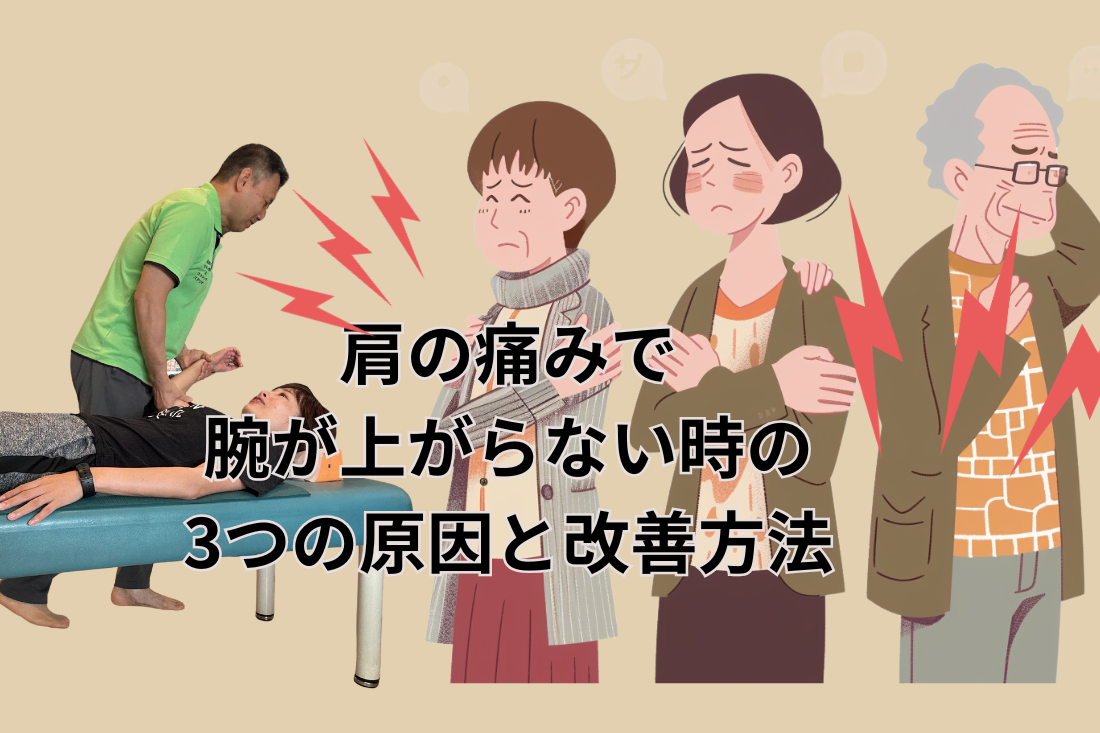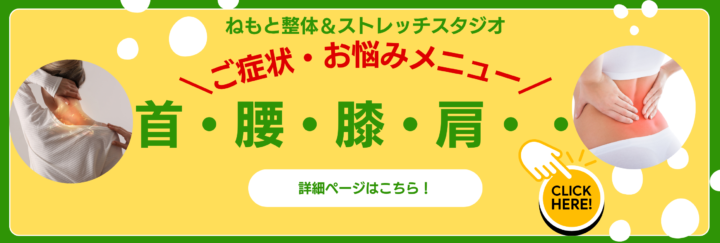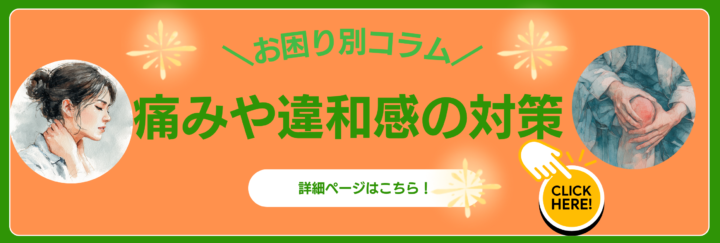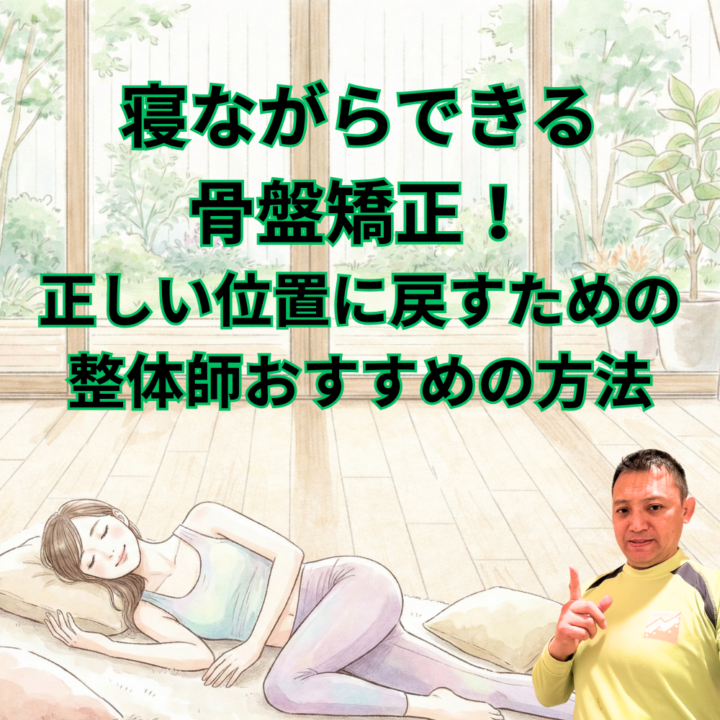服を着るのもツラい肩の痛み、なぜ上がらなくなるのか?

向ヶ丘遊園ねもと整体&ストレッチスタジオです。朝起きて服を着替えようとしたら肩に激痛が走る、髪を洗おうと腕を上げると痛みで動かせない──こうした肩の痛みと可動域制限は、40代以降の多くの方が経験する深刻な悩みです。
肩関節は人体で最も自由度が高い反面、最も不安定な関節でもあります。屈曲・外転・内旋・外旋といった複雑な動きを実現するために、骨・筋肉・腱・関節包・滑液包など多くの組織が協調して働いています。この精密なバランスが崩れると、炎症性疼痛や運動制限が生じ、日常生活に大きな支障をきたします。
病院で「様子を見ましょう」と言われ、湿布と痛み止めだけで数ヶ月が経過している方、整骨院でマッサージを受けても一向に改善しない方も少なくありません。実は肩の痛みには明確な原因があり、その原因によって適切なアプローチ方法が異なります。
本記事では、川崎市登戸で20年近く整体業を営む当院が、肩が上がらない痛みの代表的な3つの原因を詳しく解説します。さらに関節ニュートラル整体による改善アプローチ、自宅でできるセルフケア、そして手術を検討する前に知っておくべき重要な情報までお伝えします。
1. 四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)
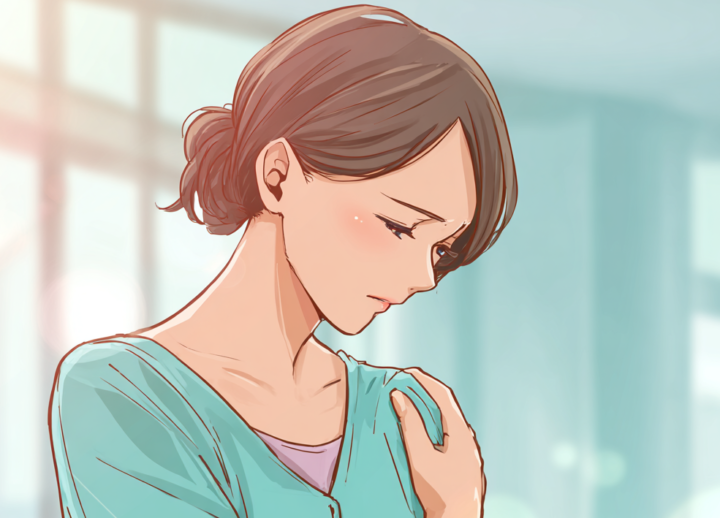
40代から50代に多く、肩の痛みと可動域が制限されます。肩関節を包む関節包の炎症で、毛細血管のようなもやもやした「もやもや血管」(異常血管新生)ができていることがわかっています。第一人者の奥野先生によると、異常な血管が過剰に増え、その周りに神経も増えてしまうので痛みが強くなると言われています。
急性期と慢性期があり、1年で良くなる方が多いのですが、最長で2年かかります。組織の入れ替わりが2年というサイクルがあることから自然に回復しますが、何をやっても1年間は痛みが強い症状と言われています。
2. 肩峰下インピンジメント症候群

この症状は、最も整体で施術後に効果が現れやすい症状です。肩を上げる際に、肩甲骨の一部である肩峰と上腕骨の間で腱板や滑液包が挟まれて炎症を起こす状態です。
しかし、この原因になるのが猫背・巻き肩などの姿勢不良です。五十肩や腱板損傷に比べて、全身の関節の動きを調整し、特に肩周りの肩甲骨や上腕骨、鎖骨の関節と体の動きをスムーズに調整していくことで痛みが消失していく方が多いです。
3. 腱板損傷・腱板炎症

肩関節を安定させる4つの筋肉(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)の腱が損傷したり炎症を起こしている状態です。転倒や重いものを持ち上げた際の急性損傷と、加齢や繰り返しの負担による変性断裂があります。実際に腱板が損傷した患者さんとお話しすると、MRIでご自身の画像を見た際に「ボロ雑巾のようだった」とお話しされていました。
これは「筋肉に穴が開いている」という表現をされる方が多いです。完全に断裂しているのではなく、部分断裂や穴が開いている方が腱板損傷や腱板断裂と診断されます。
またそこまで行かなくても炎症ということで、腱板の炎症が痛みの原因になっていることも多々あります。五十肩と言われて2年経っても良くならない方の4人に1人は腱板損傷だということがNHKでも解説されていたことを見たことがあります。
関節のアライメント不良(関節の引っ掛かり)
画像でイメージできるようにご説明します。こちらの4つの画像では、鎖骨や肩甲骨、そして上腕骨、この関節を支点として関節に遊びをつけている施術を行っています。
関節ニュートラル整体という特殊な技術を当院では採用しています。従来のもみほぐしのような施術は主に筋肉や筋膜といった軟部組織のモビリティです。これに対して関節の中、つまり関節内運動を正常化する施術として及川雅登先生が考案されたのが関節ニュートラル整体です。
大きな特徴としては、関節を8方向に圧縮と牽引、上下左右、ひねりといった全ての動きを調整していきます。施術自体には痛みは全くなく、肩の痛みが強い方でも安心して施術を受けることができます。


鎖骨の調整
肩の連動する動きを高める

痛みがない施術
痛いところまで動かさい

肩関節の外旋
動きが悪いところを見極める

関節がルーズな時は?
肩関節の圧縮で痛みを抑える
筋膜の癒着・筋肉の硬さ

肩の痛みに一般的に行われているリハビリについても触れておきます。
痛みが急性期から慢性期に入り、少しでも楽になってきたら、肩関節が固まらないように運動療法を取り入れていくことをおすすめします。
肩には「ローテーターカフ」という腱板のリハビリがあります。筋トレと異なり、インナーマッスルのリハビリとして、チューブや自分の手で負荷をかけて正しい筋肉の使い方を再教育する方法です。野球選手などは、このローテーターカフのストレッチとリハビリを常に行ってから投球練習やトレーニングを行います。
また、姿勢の問題も重要です。巻き肩や猫背による肩甲骨の動きの制限がインピンジメント症候群の原因になります。長時間のデスクワークやスマホ利用の際には、短時間でも良いので一度中断して体を動かすことが大切です。
末期は手術 その前に

肩の痛みで病院を受診し「手術しかない」と言われ、不安を抱えて来院される方が少なくありません。確かに腱板が完全断裂している場合や、保存療法で改善しない重度の症状には手術が必要なケースもあります。しかし、手術は最終手段であるべきです。
手術には必ずリスクが伴います。全身麻酔のリスク、術後の痛み、リハビリ期間の長さ、そして最も重要なのは「手術をしても必ず治るわけではない」という現実です。実際に手術後も痛みが残る方、可動域が完全には戻らない方もいらっしゃいます。
また私の周りの患者様でも手術は2週間入院と言われていました。現実的になかなか入院までしてオペをする人は相当重症な方です。
特に注意したいのは、MRI画像だけで手術を勧められるケースです。画像で腱板損傷が見つかっても、それが必ずしも痛みの原因とは限りません。ある研究では、痛みのない高齢者の約4割に腱板損傷が見られたという報告もあります。
また小学生の野球をしているかなりの子供達ですら肩が痛い子の半数が実は腱板が痛めていると言われています。
そのような人達でも9割程度の肩がしっかりと整体を受けたり、リハビリを行えば、日常動作では支障がないレベルまでは改善が可能です。
手術を決断する前に、関節の動きを整える整体、筋膜リリース、ローテーターカフへの運動療法を十分に試すべきです。
当院では手術適応と言われた方でも、関節ニュートラル整体と適切な運動指導で痛みが改善し、日常生活に支障がなくなったケースが多数あります。手術は「肩の専門医」に相談するという認識を持ちつつも、できることは全て行い改善できるものは試してみる価値があります。
肩の痛みでやってしまいがちな2つの落とし穴

肩の痛みでやってしまいがちな2つの落とし穴についてご説明します。
1つ目は「肩が痛かったらお風呂で痛いところを揉めば楽になる」という思い込みです。
昔は「お風呂に入って肩をよく揉んで」などと言われたものです。しかし、先ほどご紹介したもやもや血管の奥野先生の書籍を読むと、異常な血管により痛みが発症している場合は、血流が良くなりすぎているので肩を揉んでしまうと逆に痛みが増強してしまうということが言われています。
それよりも、血流を止めるように押すということが痛みを抑制することになります。
もう1つは、実はトレーニング、特に筋トレで肩の腱板を悪化させている方が多いです。
種目で言うと、ベンチプレスやプッシュアップなどの種目です。このメジャーな上半身のトレーニングは実は肩が内側に内旋します。やればやるほど外旋とのバランスが崩れていくので、インピンジメント症候群なども起きやすくなります。
つまり、トレーニングのエラーによる知識不足が、やればやるほど肩の症状を悪化させるということです。
肩の関節を調整法は痛くありません

長年、私は整体の仕事を行っていますが、五十肩の方でも無理のない程度の肩の調整は行っています。
五十肩は「フローズンショルダー」と言われて、凍結しているように動きが制限されています。それを無理に動かすことは全く必要ありません。痛みがあるような強い刺激の整体は、かえって痛みがひどくなる可能性があるので五十肩の方は注意してください。
また、多くの整体や整骨院などの施設で「時間でこの痛みが解消する」ということを知らされていないケースがあります。特に五十肩は1年で良くなる方が多いので知っておいてください。
腱板損傷に関しては、これも時間である程度楽になるケースもありますが、逆に言うと損傷しているので、五十肩と比べて痛みを引きずる可能性があります。場合によっては手術も検討する必要があるので、自分だけで判断せず、手術経験が豊富な専門医に一度見てもらうことも検討してみてください。
インピンジメント症候群に関しては、知識がある治療家の先生に体全体のコンディションと肩を両方見てもらってください。そうすることで、運動療法がかえって皆さんの体を改善するきっかけになる可能性が高いです。
あなたの理解度テスト
肩の痛み知識診断テスト
あなたの肩の痛みに関する知識レベルをチェックします。正しい理解で効果的な改善を目指しましょう。
Q1四十肩・五十肩の特徴
Q2五十肩の回復期間
Q3インピンジメント症候群
Q4腱板損傷の診断
Q5関節ニュートラル整体
Q6セルフケアの落とし穴
Q7トレーニングの注意点
Q8手術の判断
登戸ねもと整体&ストレッチスタジオの「当院のご症状・お悩みメニューまとめ」と「お困り別コラムまとめ」は下記になります。腰痛(坐骨神経痛・ぎっくり腰・分離症・すべり症・腰椎椎間板ヘルニア)肩こり(頚椎症・頚椎椎間板ヘルニア・巻き肩・ストレートネック)膝痛・腱鞘炎など症状・お悩みの個別ページに飛ぶことができます。